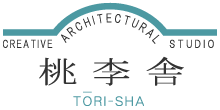トーチカ通信
[ 2022.03.02 ]本・映画・演劇・美術・音楽
戦争が始まった夜に

さがゆきさん
ロシア軍によるウクライナ侵攻が始まった25日の夜、私は心斎橋の「ザ・メロディ」という小さな店でバーボンを飲みながら、ライブの開演を待っていた。そこはコーヒーやお酒が飲めるCDショップで、夜にはミニライブも行われる。オーナーは森本徹さん。この日のアーチストの「さがゆき(Saga Yuki)」さんのことは知らなかったが、「きっと好きやと思う」と誘ってもらった。
この夜の観客は8人。7時になって、森本さんが「そろそろやろか」と照明を落とした。さがゆきさんがギターをぼろんと鳴らして歌い始めた。
不思議な声だった。1曲目はどこの国の言葉かわからなかった。ささやくような、ため息のような、低いような高いような、たとえようのない声がギターの静かな調べと一体となって、身体に沁み渡る。さがゆきさんを見つめて耳を澄ませると、声はさざ波のように、ギターの音は雨粒のように身体に届いた。私は最前列に座っていた。さがゆきさんは、目が合うたびに小さく微笑んだ。とても親密な空気が満ちていく。
さがゆきさんは50曲ほどの楽譜を用意していて、その場の空気で曲を選んでいく。
日本語の歌で意外だったのは高田渡の『生活の柄』だった。山之口獏の詩に高田渡が曲をつけた歌だ。さがゆきさんの力の抜けた歌声が野原をわたる風のように流れていく。偉ぶらず、飄々と生きた高田渡。一気に懐かしい70年代の昭和の空気が漂う。
歩き疲れては
夜空と陸との隙間にもぐり込んで
草に埋もれては 寝たのです
ところかまわず 寝たのです
次も高田渡で『ブラザー軒』。これは菅原克己の詩だ。七夕の夜、透明でキラキラした結界の中で、「僕」が亡くなった父と妹の幻覚を見る。高田渡はいつも市井に生きる普通の人々を歌った。夫は高田渡が好きで、福島のアパートでよく一緒に聴いた。
東一番丁ブラザー軒
硝子簾がキラキラ波うち
あたりいちめん氷を噛む音
死んだ親父が入って来る
死んだ妹を連れて
氷水喰べに
ぼくの脇へ
高田渡が56才で亡くなる半年前、夫は吉祥寺の焼き鳥屋「いせや」で彼に会っている。その時の同じ話をいつも嬉しそうに私に聞かせる。さがゆきさんがMCで、会うのはいつも飲み屋と言った。きっとそれは「いせや」だ。
続いて谷川俊太郎の詩に武満徹が曲をつけた、ベトナム戦争さなかの反戦歌。
死んだ男の残したものは
ひとりの妻とひとりの子ども
他には何も残さなかった
墓石一つ残さなかった
同席の同世代が涙をぬぐっている。言葉にならない祈りが、ひたひたと部屋いっぱいに満ちてゆく。みんなが悲しみを共有していた。それが感動を増幅する。素晴らしいライブ、そして時間だった。
オンラインではなく、こうして会えるっていいな、ナマの気持ちを分かち合えるっていいな、と何度も思った。蔓延防止措置が延長され、「うん、もー、ホンマにー、なあ」と大阪弁でつぶやきながら、誰一人客が来ない日も店を開け続けてくれる森本さんに感謝!

休憩タイム

さがゆきさんと仁井先生と(撮影は森本さん)