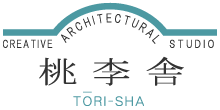トーチカ通信
[ 2026.01.19 ]本・映画・演劇・美術・音楽
座・高円寺と劇団黒テント
年賀状の別案の話の続き。
東京の高円寺で耐震改修の依頼があって、昨年から調査を始めている。11月のある日の夕方、スタッフの吉村と現地調査を終えたあと、『座・高円寺』を見に行った。それは演劇専用ホールを内包する公共の芸術会館で、建築の設計は伊東豊雄、芸術監督は佐藤信(さとう・まこと)である。
1960年代の小劇場運動というムーブメントの中で、アンダーグラウンド、略してアングラ演劇を志向する劇団がいくつも誕生した。その代表的なものに、佐藤信が旗揚げをした『劇団黒テント』がある。彼は劇団の劇作家で演出家であった。私は大学時代、演劇部でアングラ演劇をしていて、芝居はよく見ていた。中でもテントで上演する『黒テント』の芝居が好きだった。

年賀状のために作った黒テントのイメージ
『座・高円寺』は、街の中に現れた仮設のテント小屋のようだった。街路からレベル差なしで続く入口は、劇場の割には、ここ?と思うほど小さかった。テントにもぐるように中に入ると、そこには別世界が広がっていた。この空間は身体が覚えている。黒テントの世界だ。
昔の黒テントの猥雑さや埃っぽさ、思想性は、公共建築なので、きれいに消されている。それでも、鉄板と薄いコンクリートから成る幕によって閉ざされた空間は、怪しげで、前衛的だった。佐藤信はポスター1枚の貼り方にもこだわったというが、確かに大判の上演ポスターを並べた壁からは、かすかに反体制的なにおいがした。

劇場の壁面に吊るされた過去の上演ポスター
建物のことは図面と写真で予習していたし、伊東さんから、直接お話も伺っていた。ところがそんな予備知識や建築批評のスタンスは、建物に入ったら消えていた。私は全身でこの空間を感じ、味わっていた。
学生時代に演劇部でやっていたことは、芝居で誰かになる練習ではなく、舞台という非秩序、非制度の空間で自分を生きることだった。日常の居場所こそが、与えられた役割を演じる舞台であるという逆転の発想から、日常生活での自分の声、言葉、身体を疑い、演劇空間で実存を確かめようとしていた。
二つ前のトーチカ通信の「みゃくまる」で書いたように、昨年の政権交代以降、私は暗鬱な気分が続いていた。それが、この劇場に入ると、霧が晴れるように消えていった。私の心身が自由に呼吸をし始めたのを感じ、さっきまでいた外の社会の影響の大きさに気づかされた。この国を望まない方向へ導こうとする大きな力に抗いたいが、すべがなく、無力感で身体がこわばり、呼吸が浅くなっていた。ところが、体に柔軟さが戻り、私は自由な感覚を取り戻していた。それは間違いなく、建築の力だった。

劇場の2階のカフェ 壁際には本が並んでいる
その日は少し特別だった。『東京国際ろう芸術祭』の初日だったからだ。ロビーもカフェも人はいるがとても静かだった。色々な国の人が、手話で表情豊かにコミュニケーションをしていた。薄い壁の外に広がるパラレルワールドでは、強く、断定的で攻撃的な言葉があふれているが、ここには、相手の言葉を理解しようとする、つつましい努力と微笑みに満ちていた。2階のカフェでは、食器が触れ合うかすかな音をBGMに、美しいサイレント映画のような風景が広がっていて、私は言葉を失って立ち尽くしていた。
「建築の力を信じ、さぁ今年も、いい仕事をしよう!」そんな気持ちを年賀状でシンプルに伝えようとしたのだけど、小さな紙面に合わせて言葉を削ると、意味がわからなくなり、あきらめた。これが年賀状について話したかったすべてである。